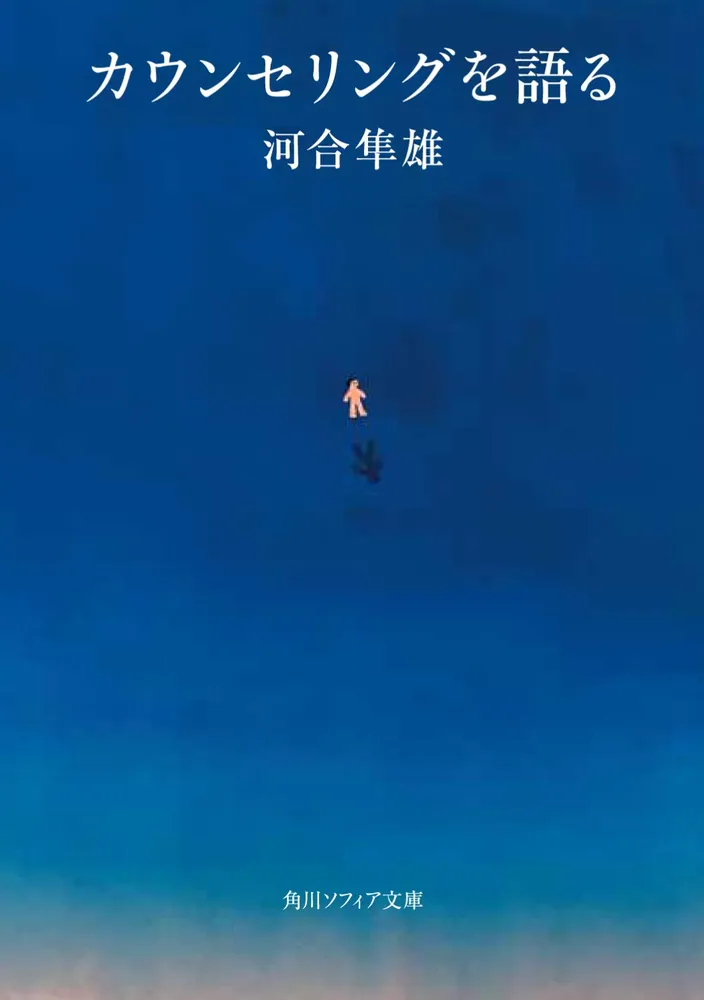河合隼雄「カウンセリングを語る」「カウンセリングの実際」「心理療法序説」より
―共感とは―
自分で体験していないことでも、類似の体験から膨らませて想像することはできる。草花を踏んでしまったことを深めていくと、人が死ぬ感じ、人が殺されることへもつながっていく(仏教的死生観)。
心理療法とは、その人の潜在的な可能性を育てること。治っていくのはその人自身の力。しかし最初は否定的な形で出てくることが多い(生きたいがための自殺行為、自立のための家出、万引き、非行、教師への反抗、親殺し等)。それらをいっしょに乗り越えていく。
治療しようと思うのではなく、その人と一緒にいて、流れについていく。ついていく自分もきちんと自分の人生を生きる(患者も自分も尊重する)。外側から観察したり、上から操作するのではなく、自らも入り込みながら、しかも足場を失わない。答えの出ない問いを二人で持ち続ける。
本当につらい時は、慰めはいらない。ただそばにいてほしい。治療者のほうがじっとしていられず余計な慰めを言ってしまう。そばにいてじっと見守り、主体性、自尊心、責任感、自立する力を育てる。ちゃんと経過を見守っていれば、よくなったことをほめることができる。これまでの経験から確信を持ってそばにいれば説得力がある。迫力が出てくる。
ロジャーズの3原則 ①無条件、積極的な関心(どんなつらい話にも関心を払う)②共感 ③自己一致(言っていることと感じていることが一致)
「父親を殺したい」という気持ちに共感できるか?「その気持ちは分かる」と言いながら内心で「殺さんでくれ」と思っていたらダメ。「殺す」と言わざるを得ない心を本当にこちらが腹の底から理解すると、そのひとはたいてい殺さない。正しいかどうかではなく、相手の痛みをこちらも感じなければならない(自分もひょっとしたら人を殺すかもしれない)。私たちが何でも聞きますと言っても、相手はどこまで受容されているか、同じ位置で敬意をこめて(尊敬して)接してくれているか分かる。
―面接の約束―
時間などの枠組みを決めることも大切。死ぬほど苦しい話を続けるのはつらいから途中から雑談をはじめることも。あるいは、面接の最後に必ず「死にたい」と言い出すことも。時間を区切ると、その人自身が考え出す。行為の意味に気づくことができる。
うまくいかないとき、相手のせいにしない。自分の荷物を相手に持たせるような言い方をしない。自分も背負って歩いている一人として言う。一緒に旅をして、成長していく。(例)患者の行動化は、治療者や親に対する「もっとわかってほしい」というメッセージかもしれない。
うまくいっているとき、相手は成長のために苦しんでいる。反省したり、深く考えたり、自分を責めている。治療者が得意になると、相手と気持ちが離れていき、すれ違う。(例)ある教師が非行少年を自分の家に住まわせて熱心に面倒を見た。すごく良くなったとおもっていたある日、少年は教師の月給を盗んで飛び出した。「先生、周囲に自慢したいだけちゃいますか。本当に僕のことを見てくれてましたか」
できないことはできないと言う。約束を守れないときは正直に話す。表面を取り繕って弁解がましくなったり、嘘を言うと相手にばれる。必死な人の勘は鋭い。「勉強会に行かなければいけない」ではなく「勉強会に行きたい」と言うほうがよい。
少年がナイフやピストルを隠し持っていた。それを親や教師や警察に言うべきか言わないべきか。一面的な絶対的に正しい答は無い。「言わんといてくれ」と言われて「できない」と答えたとして、言う言わないよりも、「少年がなぜナイフを持っていたのか」「そのことをなぜ今、治療者に告白したのか」を考える必要がある。
―治療の実際―
「仕事がうまく行かない。上司と合わない。転職したほうがいいのか」。 配置換えや転職を指示すれば問題は解決したかに見える。しかし、なぜ上司が憎いのか考え続けると、例えば父親との葛藤に行きつくかもしれない。人(外部)のせいにしたいのに自分の内面に帰ってくる。話すうちにしぜんと、自分の痛いところに自分で触れていくことになる。
物を投げたのを注意されたことがきっかけで緘黙になった少年。カウンセリングを受けているうちに、緘黙の子がクラスで物を投げ始め、他の子と投げ合いになった。誰かの頭に当たって先生が注意。「今のは僕やない」と緘黙の子がついに喋った。緘黙になったきっかけは彼を理解しない男の注意。喋ったきっかけは彼を心配する先生の注意。
また、カウンセリングは近所迷惑なもの。ずっと黙って、場合によっては虐待に耐えてくれていたほうが治療者は楽。
母親の英才教育で煮詰まった秀才の子が悪いことをする。そのことを母親に言うが、母親の良くないことも指摘する。一生懸命やれば伝わる。「子どもを追い込んだのはお母さんですよ」。治療者も同じ痛みを痛みながらやっていく。「あなたのやっていることの意味は分かるけど、その行為自体は悪いこと」を治療者の胸に収めながら行う。
かまってほしい少年が、治療者に一緒に遊んでくれ、家で飯を食わせてくれと言う。治療者は父親ではないしどうするか? うまい具合に相手してくれる年寄りの先生が現れる(世界は広い。私の限界を越えた広がり、みんなで助け合う)。その先生の手柄になってもよい。治療者はどこか片隅に座っていて、あんまり動かない。何もしないことを全力で。
意見するときは相手を非難しない。「あなたの考えはこうだけど、私の考えはこうです」と対等の位置に置く。攻撃できる余地を残し、攻撃されたらしっかり受け止める。正論ばかりの親はたまらない。反論できないから子どもは暴力を振るう。
子どもの可能性が、家族や治療者との関係の中で、ときに自殺念慮として表現される。「死にたい」という子どもに「生きてたらいいこともあるかも」とつぶやく。すると「その程度のことしか言えないのか」と迫ってくる。そこで圧倒されずに「そうや、その程度なんや。あんたのほうが生死についてずっと考えてるんやから、もっといいこと浮かぶんやないか」。すると相手が自発的に考え出し、その子の可能性が動き出す。「生きることは苦しい。だから生きたい気持ちを表すには死にたいというしかなかった。」
―相手の力を利用 / 主体性を刺激する―
「何か悩みはないか」ではなく「何か好きなことはないか」「好きなことはあまりないけど、あんたに話すのは嫌」。そこで叱ったりせず、「うまいこというな」と受け止めると話が進展する。 ずっと黙っている子。「来週も来るか」頷く。予約票を紙飛行機に「よく飛んだな」で「こんな折り方もあるんや」と最後に心を開く 相手はこちらの容量を測っている。
不登校の子どもにしばしば完璧主義がある。一度行けないと完璧じゃなくなるから、その後もずっと行けなくなるのだ。いつも時間ぴったりに入室する少年。「1時間前から待っています」。思わず驚く。「すると君は今まで一度も遅刻したことがないのか!」遅刻どころかずっと不登校であるのにとお互い笑う。
少年の好きな碁や将棋をする。し続けて、ついに先生が負かされるようになった頃にその子が学校へ行くようになる。勝負をする過程で同時並行で彼の問題が処理されていく。
頭ごなしに「学校に行きなさい」ではなく、ただキャッチボールをするとか、まず、その子の興味があるところからやっていく。(例)ロケットに興味がありひたすら調べて話をする子ども。「ロケットが大地から離れていくイメージ(母親からの自立)」を抱いて話を聴く。解釈は告げない。本人がどう動いていくか見守り、ついていく。
「諸悪の根源は母親だから母親がカウンセリングを受けるべきだ」「私は諸悪の根源に会う力まではない。その息子になら会えるかもしれん」と返したら子どもが興味を持った。
父親が「子どもが不登校になった原因は自分じゃない」と力説してくるなら、「原因はともかくとして一緒に何ができるか考えましょう」と伝える。非難されないと分かると父親は安心して冷静に考えるようになる。「私の態度にも問題があったかも」と言い出す。それを褒めると、ますますお父さんは自発的に考えてくれる。
担任の先生が「あれは非行少年だからどうしようもない」と延々と語る。ふんふんと感心しながら聞いて、「なんともならんのでしょうな」と感想を述べると、今まで否定していた先生のほうから「いやいや、こんな良いところもあったりするんです」と言い出す。「さすが先生、生徒のことをよく見てますな」とすかさず褒める。
偉い先生の息子が放火して家出しようとした。「親父は最高だけど、俺は勉強はできないし最低のことをしてやろうと思った」「偉い先生が自分の息子を救えないのはおかしい。お父さんは最低や」と伝えると息子は喜ぶ。そこで、「あなたは自分で最高の生き方を探さなければならない」と伝える。
―実存/認知行動療法的な考え方―
妄想をとって普通の人にしてやろうと考えるのではなく、妄想があるなら、ただ、あるということを尊重する。良いとか悪いとか価値判断はしない。妄想によってどんな苦悩をやわらげているのか。妄想を通じてどう変化していくのかが大切。嫌で仕方ない幻聴にも意味がある。幻聴がとれてなくなっても、隠されていた真のつらさが顔を出すかもしれない。幻聴がとれて普通の生活に戻るとき急に怖くなる。
行動療法で、階段を3段しか登れないのが5段しっかり踏みしめて登れるようになったとする。表面的な変化に見えて、内面でも深い変化が起こっているのかもしれない。心が治る過程で体の病気になることもある。無意識と身体感覚はつながっている。原因を探らなくても治っていくことがある。
言語化したり解釈しすぎれば、大切なもの、その人が生きていること自体が損なわれる。「夢の中のライオンは怖い父親だ」と決めてしまうと終わり。その人の中でそれ以上イメージが発展しない。
恋人が交通事故で死んだ。なぜ私と生きることができずに亡くなったのか?必要なのは「頭を打ったから」というような医学的説明ではない。 嫁の悪口を言いに来る姑。「その嫁はあなたにとって『牛に引かれて善光寺参り』のその牛です」と伝える。自分はなんで嫁の悪口をずっと言っているのか?その背後に老いて死ぬことへの恐怖があるのかもしれない。ドラッグをやる少年。どういった深い問題があるのか、周囲に何を伝えようとしているのか。ドラッグをやめて、元の良い子に戻るのではなく、どう生き方が変わるのか。
自分の物語(成育史、連続した記憶)の中にうまくとりこめないものが、症状とか悩みとなって現れる。妄想、幻聴や、自己臭妄想、醜形恐怖、解離による記憶の欠落などの神経症。その人にとってはリアルな現実。症状はイコール「先生、このつらさ本当にわかってくれてますか?」。
心理療法家は、唯一の正しい現実があると考えるのではなく、その人が現実をどのように認知するか、その認知が、その人にとってどんな意味をもつか、周囲の人々とどのように関係するか、に関心を払う。