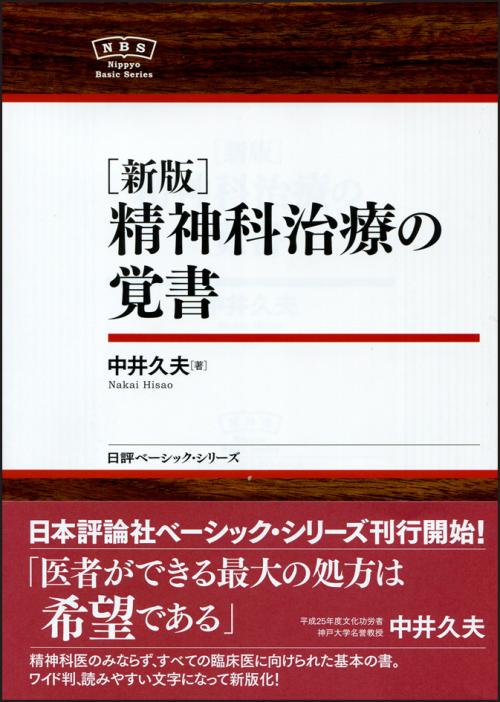統合失調症(中井久夫の著作を参考に)
統合失調症患者に対する接し方1 急性期
急性期の方は、圧倒的な恐怖に支配されています。「ちょっとでも自分が動いたら世界が壊れてしまう」とか、「宇宙戦争に巻き込まれて、怖くて仕方ないのにふりまわされている」というような。ですから彼らが暴れるのは「非常に強い恐怖のため」だと考えてまず間違いないです。興奮して飛び出す患者は「こころの平和」を求めている。木は静かになりたいのに風はやんでくれない感じ。
暴力は、低レベルで一時的ですが、精神の統一感を取り戻すことができます。頭の中が乱れてどうにも止まらない時は何か手を使うことで一種の統一感が生まれる。行為というのは一度に一つのことしかできません。大声を出すのは一度に一つのことしかしゃべれません。殴るのも一度に一つです。同時にいくつもの考えが頭の中を駆け巡っている時には統合の方向へ、自己コントロールの方向へ向かうのです。
したがって、接する者の態度はおのずと決まってきます。彼らはコントロールできない恐怖を抱えている。彼らが自分で自分をコントロールするのを助けなければいけない。そのために我々ができることは「安全を保障すること」です。我々との関わりの中で安心できる状況をつくる。暴力に暴力で答えるのは悲劇です。どんな刺激にも暴力で反応する慢性患者をつくってしまうことになりかねない。彼らが最初に暴力を振るった時はよほどのことがあったのでしょう。その気持ちを汲み、医療者は揺るがず対応しないといけません。
人が不安定になる時期があります。季節では春の4月、梅雨の6月がもっとも自殺者が多いそうです。4月は進学就職の節目だからわかるとして、6月は梅雨の不安定な天候が影響しているかもしれない。雨が降る前に人はイライラします。気圧が下がるためです。低気圧になるからではなく、気圧が下がる加速度が問題らしい。一日の中での逢魔が刻は夕方頃、4時~7時です。この時間帯が最も不安になる。だからその時間帯に不安を訴える方には「7時過ぎまで待てば落ち着いてくる」と話す。不思議とたいていはおさまっていきます。
衝動的な暴力について、我々の無意識が「あいつを殺したい」と判断したとき、意識がわずかに遅れてその情報を吟味し「考え直せ」とやる、その間0.55秒。つまり意識は無意識より0.55秒遅れで「今、自分がこう判断している」とみなすのです。当たり前の話ですが、実際に殺さなければ、誰か1人2人殺してやりたいと思う人がいてもかまいません。なぜ実行に移さないかといえば、0.55秒遅れで「待てよ」という意識(=良心)が働くからです。無意識の殺意を完全に消すことは無理だし、しなくてよいです。
ではその無意識の衝動が抑えきれなくなったらどうすればいいか。もちろん治療的介入が必要になります。発症直後の混乱している方に服薬させる時はこう説明する。
「私は医者です。あなたがとてもつらい状態だと判断するから、薬を私の責任で飲んでもらいます。いいですか。今はそう思えないだろうけど。30分くらいしたらしだいに落ち着いてきて1時間もすれば頭の中の乱れている考えがずいぶん整理されてきます。」「あなたは頭の中が忙しすぎて、考えがいっぺんに押し寄せてまとまらないのではないだろうか。この薬は頭の中をきちんと整理するもので、気持ちよく眠って目覚めたら、いいほうへ少し変わっていると思う。私を医者として信用してほしい。」と伝えます。彼らは聞いていないようでちゃんと聴いています。これを怠ると「医者の薬のせいでバカにされた」と、薬を飲んでくれなくなります。
彼らは何を知りたいと思いますか。病名よりも、「これから私はどうなるのだろう」ということでしょう。病気になったということは、思いがけない、いわれのない事件で逮捕された時と同じです。そういう時にいきなり「君は挙動不審で逮捕された」と言われても「どこが不審(病気)なんですか」となってしまい不毛です。逮捕された時は「これからどうなるのか」が不安で一番知りたいはずです。まず医療者は「あなたは一生に何度かしかない非常に重要な時にいると私は判断する」と伝えます。患者さんの中には、一生懸命がんばってきてもう少しで悟りに達する直前に医療者に邪魔された、薬でバカにされた今より、治る前のほうがずっとよかったと考える人がけっこういます(発症時の圧倒的な恐怖は万能感と表裏一体です)。ですからとにかく「医療者がそう判断する」ということを伝えます。
治療の必要性を家族のせいにしてはいけません。それから家族の方には「大切な子どもさんをやむを得ず、このようなことで申し訳ありません」と謝ります。家族はわっと泣かれます。その瞬間、何か心が通うきっかけになります。少しでも強制的な関わりをするときは家族の方は患者に対して罪悪感を持っています。それを引き受けて軽くします。
そして薬よりも先にまず『希望を処方』します。私は「医療者と家族とあなたの三者の呼吸が合うかどうかによって、これからどうなるかは大いに変わりうる」と告げます。つまり「幅がある」「変わりうる」ということです。患者さんはこういうときの言葉を一字一句何年でも覚えています。かれらにとって本当に人生のるかそるかの時ですから切迫感があるのです。
「統合失調症」という病名を告げることよりも、本人が「物凄い悪夢から逃れた」と感じて、「よくあんなことを乗り切ったもんだ」と思い、だんだん記憶が薄らいで忘れていくというのが一番よい治り方です。病気を診断することよりも、かれらが持つ回復力、忘却する力を育てることが大切です。そのために「あなたができる協力は、第一に都合の悪いことを言うことです。そうでなければ私はきっと間違って判断するだろうからね。」と告げます。次回面接は「今晩眠れたら翌翌日、眠れなかったら翌日」に設定します。眠れたら寝かせてあげたほうが回復は早いです。最初の処方は「最低量だから効かなくても量を増やせるし、別の候補もたくさんある」と前置きします。
薬の飲み心地を問います。同じように睡眠についても眠り心地を問います。食事については「味がわかるようになったか」と聞きます。精神のゆとりがない時、味はわかりません。その上、味に注意を向けることは、実は肥満を防ぐ一番簡単な道なのです。水を飲むにしても、どういうふうに気分がいいか、どんなふうに気分が変わるかということに着目するのはよいことです。これが協力であり、「苦情を言うことが最大の協力である」ということです。こうやって説明すると最小限の苦情しか言わなくなります。
保護室へは最初は2人以上で行ったほうが相手も安心します。1人だと何されるかわからないでしょう。それから正面から向かっていかない。目には威圧力がありますから、目をつぶるくらい、顔を見る時はやんわり鼻の根元とか、少し下を見るのがよいと思います。
話す前にまず身体診察をします。脈を診たり、聴診器を当てたりしていると多くの方は落ち着きます。聴診器を当てることで「待ち」の時間、結論までの猶予を生み出すことになります。そして「ほんとうは大丈夫なんだよ、今はそうは思えないかもしれないが、大丈夫だと思う。」と小声で、あるいは心の内でささやきます。こういうときは声のトーンが一番重要です。ふわりと相手の肩を包むような声というか、低く、やわらかな小声です。混乱し神経過敏になっている相手には大声や細かい話は禁物です。
「きみには到底そうは思えないだろうけど」というのは相手の気持ちを汲んでいるわけです。そして「ほんとうは大丈夫なんだよ」と言う。彼が何を恐れているのかこっちはわかっていない、わかっていないんですけど、実際彼の身の上に起こっていることというのは彼が自殺さえしなければ大丈夫なんです。だから嘘をいっていることにはなりません。そしてこちらの表情が「大丈夫」という言葉に呼応したものに変わります。こちらのゆるみが相手に伝わります。急性期には言語は意味よりも音調、語調の伝達性が高いです。急性期の興奮している方の中では、だいたい二つの勢力が争っていて、「イヤなのにそれに巻き込まれていると思ってまちがいないです。あるいはこれは緊張病性昏迷が解けた方から直接聞きましたが、「自分が指一本動かしたら、世界が壊れるかもしれない、私は世界に責任を持たされてしまった、なぜか知らんけど。」と言っていました。「指一本動かしてみたらとは思わなかった?」と聞いたら「そんなことをして世界が壊れたらどうするんだ!」と怒られました(この場合、本当に壊れそうなほど無力感にさいなまれているのは彼ら自身、それを「世界が壊れそう」と外へ投影している)。
興奮というのはうつりやすいので、自分が興奮しないようにするのが大切ですが、興奮の芽は自分の中にも出てくるもので、それまで止めようとするのは無用です。この芽は、自覚するとふしぎと静まります。おそらく暴力をふるう患者さんに対して医療者が興奮してしまうのは適切な対処法を知らなかったから、ということがあると思います。つまり医療者の無力感を反映しているということです。例えば、穏やかにあいさつすることは重要です。自分を脅かす敵だと思っていた相手が会釈してきたらびっくりする。敵対的に出られれば暴れられるのに暴れることができなくなる、出鼻をくじかれるんです。
幻聴を4期に分ける
1期 亡霊のざわめき、雑音をたどったらそこにあるもの
水道の蛇口から水が垂れているさま、まっすぐ垂れているかと思ったら、時々ねじれて、また垂れる。それと同じで耳の中の雑音のようなざわめきが時々声になってまた戻るといいます。考えが花火のように次々と無限に分岐していく。どんどん考えが分かれていって、コントロールが効かなくなって最後は全体が混沌としたざわめきになる。
発病時に「頭の中が騒がしい」という感覚がある。コントロールを失いつつある感じ、自分と世界の境界があいまいになっていく過程です。発症前は、何も食べなくていいし、死なないという不死感がある。というか死との境もひとまたぎで越えられるくらい近くに見える。ひょいとまたいだら世界の向こう側にいける感じ、このときは自殺のリスクが高いです。
2期 世界全体が叫び出す
ムンクの絵にそういうのがあるでしょう。緊張病性興奮の時は、いわば世界が揺れてやまないので一緒に揺れているんです。それがつらい。一方、昏迷になっておられる人は、揺れに抵抗してじーとして動かないわけです。筋肉を動かしている時と、じーとしているのと、どっちが楽かというと動いているほうが楽なんですね。じーとしているほうがものすごくエネルギーがいります。だから昏迷のほうが大きく世界の叫びを聞いている可能性があります。指一本動かしたら世界が崩れるというのは魑魅魍魎の世界なんですね。自分はその侵略に対して世界が崩れないように支えている。つまり自我(=世界)の崩壊を、自分でかろうじて支えているというふうに翻訳してもいいんでしょうけど。
3期 精神に自由が回復してくる時期
不可解に変化していく世界を理解するための苦肉の策が妄想です。だから、この時期の妄想は自由連想。思いつくままにどんどん変わっていきます。しかし自由連想というのはゆとりを消費しますから長くは続かない。だんだん限られた内容になっていきます。繰り返しのほうが楽ですから。しかしそこに妄想が固定化するワナがあります。
幻聴の内容は、自分が言っていると思ったらたまりません。自分が言っていると自覚することを「自己所属感」といいますが、幻聴は自分が言っているわけではないから、自己に責任はないわけです。「殺す」という幻聴は自分が殺すのではなくて、必ず他人が殺すと脅かしていることになっています。
ただ、誰かが自分に向かって言ってきていることだけは疑えない。疑うゆとりができたら統合失調症の幻聴ではありません。幻聴の正しさを主張する統合失調症者には「ふーん、ふしぎだ」「あなたが聞こえる実感は私の理屈より強いでしょうね」などと答えるといいでしょう。フランスの精神科医アンリ・エイは「共同体からの疎外というものを我々は恐れている。だから幻聴の内容もそういうものになる」と言っています。「共同体からの疎外の恐怖のほうが快楽の追求より強い」と統合失調者の幻聴の話を聞いていると思います。
4期 安定期
幻聴はしだいに1つのテーマに絞られてきます。それからの運命は状況によって違います。そして次のような時には消える前兆です。入浴中、朝の寝床、寝る前のリラックスした時、急に静かな所へ移った時に聞こえる。その場合は内容も必ず穏やかになっています。
幻聴が消えかかっている時には「幻聴とあなたが呼ぶもの、それが消えてしまっても大丈夫か? ずっと慣れたものと別れるのは寂しくない?」と言います。これを会うたびに何度もしつこくたずねます。相手は「大丈夫です」と言うんですね。むきになって「大丈夫!」と言うこともあります。この問いかけも幻聴の消失に一役買っているんでしょう。
鼻の頭にほくろのある女性がいました。これを手術でとったら、寂しくなったと言って、どういうことなのかよくわかりませんが自殺したそうです。例えほくろ一つとっても寂しくなって死にたくなる。一見小さいことが気になる、私が私であるための特徴なんでしょう。ましてや幻聴ですからね。消えると寂しい。消えても寂しくない時におのずと消えるんです。逆に情報から遮断されているときは幻聴はいつまでも消えない。
ある20年以上入院しているおじいさんで、奥さんはとっくに亡くなっているんですが、「奥さんが生きている」という情報がTVから入ってくるというんです。「本当だと思うの?」「いや本当かわからんが、他に知る術がないじゃないですか。」
ある若者は薬で幻聴があっさり消えましたが、そのとき彼はこう言いました。「たしかに幻聴が続いている間は苦しい。しかし薬で消えたときには、また起こりはしないかという恐怖が私を占める」と。薬で消せばいいっていうもんでもないと教えられました。幻聴はかさぶたがはがれるように自然に消えていくのがよいようです。
こちらが相手を見るのに病理中心だといけません。健康な日常生活を中心にしなければ。病理中心では「自分の最低レベルで評価されている」と感じます。そこで自分の最高を示そうとしたら妄想が強化されるかもしれません。
実感は論理より強いです。他の患者さんが話す妄想はバカにできるけど、自分が感じている幻聴は本当だと思うものです。論理は間違うことがあるけど、実感は間違うことが少ないというのが我々の経験じゃないでしょうか。
レイブラッドベリの「火星年代記」というSFに、火星探検隊の地球人の脳からデータをとって、火星人が地球人の幼い頃の街を再現する場面があります。その地球人のおじいさんとおばあさんが出てきて「どうしてこんなことが?」「そんなこと考えなくていいじゃないの。私たちはいまここにいるんだから」とおじいさんたちに言われる。懐かしいお菓子なんかをふるまわれて、その地球人は寝入って永久に目を覚まさなかったという話です。たとえ私たちの祖父母が蘇っても、いきなり「お化けよ、去れ!」なんて言わないでしょう? ましてや荒涼とした火星でそういう温かみのあるものが見えたら、論理的判断は後回しです。「いまここに祖父母がいる」という実感を信じてしまいます。
なぜ幻聴や妄想を嫌わないか
妄想を話す時の彼らの口調はどこか平べったいです。妄想には心というか、情が通ってないんです。でも通ってないからこそ「世界がどうにかなってしまう」という大変なことも話せる。彼らの中で物凄く大きな変化が起こっているわけですから、もし感情をこめたら大変なことになってしまいます。彼らの中で何かがぷつんと切れているんです。たぶん妄想とか幻聴というのは一度に一つのことしか頭の中に浮かばせないようにするためにつくられているんだと私は思います。言葉というものはそういうものですから。発症初期は同時にいくつものことが頭に浮かんできてまとまらない。思考が逃げ道がない袋小路にはまりこんでしまう。そんなときにたとえ幻の声であっても一度に一つのことに統一されるのは助かることなのです。
海外で単身赴任で働いている方に聞きますと「独り言を言わないと狂うよ」と言います。
孤独をまぎらわすために、その日したことをいちいち声に出して言ってみるのですね。自分自身で会話している。統合失調症の独り言にもそういう側面があるかもしれません。恐怖や孤独感を脳が必死に整理しようとしている。実際、独り言や幻聴、妄想の内容自体は問題ではないと思います。恐怖や孤独感を背景に出てくるから怖いのでしょう。恐怖が土台にあるんです。幻聴や妄想が、空耳とか空想と違うのはそこでしょう。
ではどうしたら幻聴や妄想を実りのあるものにできるか。私はまず「幻聴が消えうるものである」ということを伝えたいですね。そのために例えば「あなたのいう幻聴と言うものが夢の中に出てきたら教えてください」と言います。なぜ統合失調症の妄想や幻聴は夢に出てこないんでしょう。またストレスと同じように胃潰瘍になったり、髪の毛が抜けたりしないんだろうと。逆に言えば「つらさをみんな頭で受け止めている」からなのです。いわばヘディングしている。なぜ夢の中に幻聴が出てこないか、ほんとうのところはわかりません。ただ一つ言えるのは「夢のはたらきによって、我々は健康を保っている」んじゃないでしょうか。昼間にこなせなかった心の中の作業を寝ている間にこなしている。ちょうどグリム童話の小人みたいに。寝ている時には外からの情報ははいりませんし。
相手が聞き飽きたことは言わないほうがいい
例えばアルコール依存症の人なら「お酒やめなさい」とさんざん言われているわけです。同じことを繰り返しても無駄です。どこか新鮮味というか驚きがある必要があります。今まで言われたことのないことを言う。精神療法ってそういうことです。今まで聴いたことのないことを聴いて、その人が「何だろう?」と自分で考えるようにすることが精神療法なのであって、言葉の理屈で言いくるめて治るものではないです。相手の考えを広げていく。自由にする。そのためには「またか」ということは話さない。釘を同じところに何べん打っても固定しないでしょう? 別のところに釘を打つことが大事なんです。
精神科の専門用語を使わないことも大事です。幻聴じゃなく「君が聴こえる声」とか言います。「空耳というのもあるよね」「それとは絶対違います。」「どこが違うんでしょうか」などと会話が続くと、本人が幻聴と空耳がどう違うか考え出す。それ自体が本人にとってプラスになります。自分で考えるから受身じゃなくなるんですね。相手の語る妄想を毎回聞いていることは大事みたいです。こちらから聞くのでは」ありません。私は「わかった」とも「わからん」とも言いません。「ふーん」「なるほど」「不思議だねえ」「そういうこともあるんですかね」と。
医療者として患者さんに何を言ったらいいのか。少なくとも言い訳はしないほうがいい、それよりも患者さんとの約束が守れないとわかっていたら、あらかじめ断りに行ったほうがよいです。会えない時は会えなくていいんですよ。
それから「ねばならない」という言い方はしないほうがいい。「学会に出なければならない」ではなく「学会に行きたい」と自分の意思として表現する。それから断り無しに約束を破ることは人間社会の最低のルールを破ることですからね。あいさつをすること、約束を守ること、この二つをまず患者さんに行うことが治療的です。これは精神療法の基本であり大きな一部です。精神療法家をめざしているのにこれが出来ない人がいます。基本を忘れて行う特殊な精神療法ほど有害なものはありません。
慢性期の患者さんで「すぐ退院したい」と言う人がいるでしょう? すぐ退院させてくれということは「治療は自分になんの役にもたっていない、病院にいても実りがない」と思っているということです。そういうとき私は率直に告げます。「ひょっとしてそう思ってるんじゃないか?」と。相手は「そうだ」言います。うーんと考えてこう告げます。「私が診てるということは、私はさじをなげていないということだ。お前さんから先にさじを投げないでほしい。」と。心をこめて言えば退院要求をしなくなります。患者さんが何か文句を言ってくるとき、一番大事なのは患者さんの士気を維持することです。「今はうまくいっていないけど、私たちはさじをなげていない」というサインを送ることが非常に重要です。
では「俺は病気とは違う。これは私の性格です」と言われたら、「え!君は生まれてからずっとこうなのか?」と疑問を投げかけます。「生まれてからずっとこうなのか?」と聞き、「いついつからです」と答えたら「始めがあれば終わりもあるよなあ」「あるようにしようなあ」「あるようにもっていきたいよね、運もあるけどねえ」と持っていきます。「運」という言葉を私はけっこう患者さんにつかいます。我々が治してやったなんて思わないですね。「引き潮と満ち潮の時がある」「向かい風と追い風の時がある」「今はまだ向かい風だなあ」というように。
だって病気と関係なく、人生自体そうでしょう? 自分の力で切り開いてきたように思いがちだけど本当はそうじゃない。何の事件もないときもあれば、ばたばたと肉親がなくなったり思いがけないことが次々起こるときもあるでしょう? まあだいたい追い風4年向かい風3年といいますね。人生6年周期だというのは、小学校が6年で中高合わせても6年と、だいたいそんなところで決まっている。6年前後の周期で考えると気が楽になります。
それから子ども時代のことをポツポツ聴くことがあります。楽しかったこととかね、すると思いがけないことを話したりしますね。「楽しかったことは一つもない」と言われる方がけっこういるんですけど、病状がよくなってきたら楽しかったことも話してくれます。
つらいときは楽しいことを思い出せないものです。「人生今まで暗いことばかり」と言う人もいますが実際はそうじゃないことが多い。生理的に楽天的になることが健康を取り戻すことなんですね。
2 回復期 山を降りるということ
急性期は、保護室によって守られているという感じをもつ患者さんは少なくありません。自分を迫害している者も、まさかここまでは追いかけてこないだろうと。だから保護室から出す前にしばしば予告します。「ひょっとしたら君はこのまま回復していくかもしれないけど、保護室から出るのはいいことばかりじゃないよ。」と。「大勢の人が居て、中にはうるさい奴もいる。テレビも鳴っている。それでも出ていいかい?」と。自由に当惑する人もいますから。
出たら「ああ、出られたの。良かったね。」という顔をしていいし、そういう言葉をかけてもいいんだけど、保護室の中であらかじめマイナスのことを告げておくと「言われたほどじゃないじゃないか」とほっとする。マイナス要因を教えておくとプラス要因が際立つのです。「いろいろあるよ、いいの?」と聞いて「大丈夫です」と言ったら「ほんとうに大丈夫だね?」としつこく聞く。これがミソです。戻りたい人は戻ってもらっていいのです。
もし~だったら~だろうよ
患者さんへの語り口としては「もしCIAがあなたを迫害していたとしても、ここまでは追いかけてこないだろう」というふうに「もし~ならば」(=if)の表現がやわらかです。
「もうCIAは追いかけてこないよ」とこちらで決めてあげても悪くないですが、患者さんの考えを育てるのは「if」のほうでしょう。こういうやわらかい言い方は大切だと思います。幻聴についても「ああ、君が幻聴というものね、ああそう」というような感じです。それで「もし幻聴がそういってるのなら、それはつらいね」「でもふしぎだね」と続けます。徐々に患者さんと妄想の間に距離ができます。患者さんはストレートな考えしかできないために病気になっている面もあるので「こうかもしれないけど、ああかもしれない」というのはエネルギーがいるんですね。ストレートにひとつのことだけ考えるのは楽なんです。
治りかけというのは非常に大切な時期です。保護室から出る時の患者さんはとても寂しいです。運動場を友達に遅れて周回遅れで走っている感じ。社会が遠くに見える。その寂しさというのはいわば人間的な孤独感であってとても共感できます。むしろ幻覚妄想というのは、感覚をわずらわせて、その孤独を覆い隠すために機能しています。この時期をどう過ごすかによって慢性化するか、回復するかが決まると思います。病気が起きる時というのは登山に例えられます。しかしそのときは医療者は直接見ていません。医療者が立ち会うのは病者が病気山を降りる時ですね。回復というのは登山ではなく下山なのです。
最初は岩場なんかをつたいながら降りますよね。墜落の危険もあるし、ああいうときは返って用心しています。岩場を降りたらお花畑です。はじめて下のほうが見えます。上昇気流に乗って列車の音が聞こえたり。そういうときって「もうこれ以上降りたくないなあ。ずっとここに居たいなあ」という気になります。だってこれからまだまだ大変でいろんな苦労が待ってるんですよ。それを思うとうんざりする。お花畑で1時間や2時間寝転んでいたい。けれど日が暮れる前に山を降りなちゃいけない。
例えば八ヶ岳に登って、一番高い赤岳から降りてくるとお花畑があるんですよ。下を走っている列車がはっきり見えます。「一気にあそこまで行けたらなあ」と思ったりします。これが自殺に行き着くことがあります。
弓は満々としぼって放つ
保護室を出た時、あるいは急性期を抜けたときというのは、それと同じ状態なのです。しかし同時に一見正反対の状態でもあります。コンラートが指摘しているように、このときは何でもやれそうな気になる。「一過性の自己価値高揚」というのですが。でもこれは山頂からまだあまり下っていないところのお花畑なんです。でも実際になんでもできそうな気がする。「すぐ家に帰りたい」「就職したい」と言ったりします。長期的にみるとこれは早咲きの花です。霜に耐えない。そんなとき「まだ早いよ」とは言わない。「3週間待って気持ちが変わらなければやってみよう」と言えばその間に多くは忘れ去られます。
この時期に画用紙を渡して「自由に区切ってくれ」というとそれができない。そもそも「自由という意味がわからない」と言ったり、ものすごく疲労を感じる。決断するだけのエネルギーがまだないのです。ですがそのとき患者さんに恥をかかせないようにするのが大事です。とにかくものを決めるということは一番エネルギーがいるんです。就職先だって、パートナーを決めるのだって、何だってそうです。物を捨てるのだって大変でしょう?部屋を整理して、これは捨てようか捨てまいかと考えていくとものすごく大変。選択というのは人間にとって一番エネルギーを食うものです。ですから回復の初期にはこれができない。
一過性の自己価値高揚は1週間くらいしか続かない。この1週間に、意欲が出てきたからと退院させたり働かせてもたいてい続かないです。それで挫折感が重なってきたら慢性患者になります。ですからここで挫折感を味あわせないことです。弓で言えばギューと引き絞って、じっと待ってから矢を放つのが社会復帰なんです。ちょっとつないで飛ばしてもそんなに飛ばない。弓は満々としぼってからパッと放す。
妄想を語れるようになる時期
この時期に特に医者が間違えやすい。カルテを見るとこの時期に妄想を語ることを「妄想の再燃」とよく書いてある。そうではなく妄想を言葉にできるくらい妄想から距離ができたのです。妄想を総括してまとめて捨てて歩み出す。その準備の時期なんです。妄想と一体化しているときは何も言わないです。一体化したら喋れない。「過去をふりかえって」という形でしかわからないこともあります。妄想もその一つです。ふりかえって初めて言葉になるのです。そういうときは「おお、話せたね。そういうことだったの。そうだとしたらふしぎだね。」「ふしぎですけどそうなんです」「そうだね。ふしぎだねえ」というくらいのやりとりでいいと思います。異常はそこを抜け出してふりかえってみないとわからないのです。軽いうつなんかもそうでしょう。あのときはうつだったのかと。
ただ、妄想とは病気の本体ではありません。妄想はなんといっても世界の出来事の一部にしかすぎません。CIAだって何だって宇宙の出来事のごく一部です。世界が、宇宙が、全体として恐怖そのものになるのが病気のはじまりにありますから、その恐怖に比べれば妄想は何ほどのものでもないと言った患者さんもいます。
妄想とか幻聴というのは外の世界に目を向けるための、生体の防衛反応なのかもしれません。形のない恐怖に直面することはものすごく怖いですから。まったくの暗闇を歩くのは怖いでしょう? ちょっと何か見えたら(それが妄想でも)すがりたくなるでしょう。
雨降って地固まる
かつて「統合失調症ではことわざの意味を理解できない」と言われました。が、それは違います。正確には相手の言葉の含み、言外の意味を理解しにくいだけです。ですから実感として理解しやすいことわざはよく理解されます。「出る杭は打たれる」なぜ自分だけ狙われてしまうのか、悪口を言われるのか。発症前後の状況です。「おぼれるものはわらをもつかむ」病気におぼれたら、わらのようにたよりない妄想でもすがりたくなります。「雨降って地固まる」よくなってきた患者さんは実感されます。患者さんに「病気の前に戻ればいいのではないです。病気になる前というのは、いつ病気になってもしかたのない不安定さがあったんじゃないですか」と聞くと皆うなずかれます。病気の前より地を固めないといけません。
眠りは7人の小人
睡眠によって回復の程度を計ることを続けているとだんだん患者さん自身に計ってもらうことができるようになります。睡眠はグリム童話の「7人の小人」です。夜のうちに掃除しておいてくれる小人たちが睡眠です。睡眠の程度で、1番悪いのが「寝られない」です。2番目が「寝てもすぐさめる」3番目が「眠っても寝た気がしない」、4番目が「いくら寝ても寝たりない」。それ以上は熟睡感、寝覚めのよさの問題になります。
また「眠りにくい」と訴える患者さんには「眠れたらしめたものだよ」とポシティブに言い換えます。睡眠は48時間で収支を合わせたらいいです。前の晩に寝たりなかったなら今晩は早く寝る。それで再発を防げます。
回復には必ず揺れ戻しがある
回復に向かう変化の過程には必ず揺れ戻しがあります。そういうとき、慌てて処方を増やすより「すべては一時である」と告げ、様子をみるほうがいい場合もあります。変化が大きい時は、よい芽とわるい芽の両方があります。よくなるチャンスなのだけど、わるくなる可能性もある。例えば、がんばって外に出てみようと図書館に行ってみた、その晩に悪夢を見たというふうに。新しいことをすると反動があっても不思議ではないのです。人生でもそうですね。思春期、青年期は変わる力が強い。だから非常に危ない時期です。中年期はどちらかと言えば維持期で、更年期はまた変化の時期でよい芽とわるい芽の両方があります。
病気中心の人生にしてはいけない
回復期において、患者の健康な生活面に着目する。そこにこそ身を乗り出して聞くべきことがあります。患者さんがすすんで病的な内容を医者に語るとき、どうしてもそれをノートしてしまうし、身を乗り出して聞いてしまう。しかし患者が医者に多くのものを与えた場合、その患者の予後はよくないです。病気中心の人生にしてしまう。非常に驚くべき病的体験、例えば世界が粉々に分解するとか、まだ誰も報告していない現象を話してくれる患者がいたとします。その現象を熱心に掘り下げれば、彼はどんどん病理の深みにはまっていきます。
逆にその彼が、友達と喫茶店に行ったり、キャッチボールをしたりしたことを、驚くべき病的体験よりも身を乗り出して興味深く聞くべきなのです。そうやって彼の健康な面に光を当て続ける。健康な生活への注目は、まず身体診察です。生活の基本は睡眠であり、夢であり、身体症状です。ちなみに中国医学の優れたところは患者に食物の「好み」を聞くことです。人生をそういう面で捉えようとするわけですね。
私は回復の初期に身体症状が現われるということを強調しています。その程度が問題ではなく、医師が身体症状に注目して話を聴く、ということ自体に意味があるのかもしれません。例えば急性期の患者さんはだいたい便秘があります。だから「あなたはどう?」と聞いて便秘薬を出す。「あなたは不安でしょう?」と最初から聞いても患者さんは信用してくれません。
からだは揺れる-突変性
回復初期には様々な身体症状が出ますが「突然現れて突然消える」のが一つの特徴です。ある日下痢がはじまったと思ったら1日5回とかトイレに行き、ある日突然止まる。何十日も微熱や高血圧が続き、ある日急に下がる。何かと交代に現れることもあります。パーキンソン症状も出やすい。抗精神病薬が身体の中で余ってくるのかもしれません。
あわてずちゃんと身体診察して抗精神病薬はむしろ減量。診察せずに下痢止めの薬を出したり、抗精神病薬を増量しては実りがない、せっかくのチャンスをもったいないです。
「よくなりかけの頃にはいろんな身体の症状が出るよ」と患者さんに言います。言うことで身体に注目してもらうのです。たまに急性期の患者さんで、冬に裸で寝ていても風邪一つひかない方がいますが、あれは頭でストレスを受け止めている。身体の症状が出てくるということはおそらくストレスを全身で受け止めることができるようになってきたのでしょう。こういった変化は看護日誌を見返すことで知ることができます。熱計表などはとても参考になります。
回復にはエネルギーがいる
絶えず緊張状態にいる人は痛みを感じません。交感神経が興奮しているからです。マラソンを走り終わってから疲れがどっとくるでしょう。患者さんのよくなり方はそれぞれですけど、だいたい一度元気になってそれから非常に疲れが出てきます。疲れには「柔らかい疲れ」と「硬い疲れ」があります。「柔らかい疲れ」は実はリラックスしてきたけどそれをいい感じだと受け取れず「疲れ」と感じている状態です。つまりその人は今までの人生であまりリラックスしたことがなかったか、身体が覚えていないほど緊張の連続だったのでしょう。だからリラックスした状態を心地よく感じられない。回復していく過程で疲れが出てくるのは、実は回復にはとてもエネルギーがいるからです。急性期で暴れている患者さんは実は一番エネルギーが低い時期だと思います。まとまった行動ができなくてただ興奮しているというのはまとめるだけのエネルギーがない状態です。自分の知性、感情、意志をまとめていくほうが大きなエネルギーが必要。それに比べれば赤ん坊のように泣いたり転がったりするエネルギーはたいしたことないと思いませんか?
回復には4つの段階があります。最初は精神運動興奮状態。次が幻覚妄想状態、その次が心身症、最後に非常に疲れている状態。これらの過程のどこかで足踏みしているのが慢性患者さんです。興奮ばかりしている人、昏迷で無反応な人、幻覚妄想とどこかでつながった言葉や動作ばかり繰り返す人、あそこが悪い、ここが悪いと身体の訴えが多い人、だるそうに何もしない人、慢性患者のリストができあがります。慢性患者はこのリストのどこかで足踏みしていると考えるとわかりやすいです。
快感のない(アンヘドニア)ときには人間の行動は弾みが出てきません。慢性状態はこの弾み、ゆらぎが乏しい。そこから弾みがでてきてだんだん元気になっていくというのが回復の過程なのです。そのためにエネルギーを補ってあげる。これは中国の医学の考え方ですね。西洋医学は悪いところをやっつけようとしますが中国の医学は地盤のかさ上げを視野に入れます。
回復してエネルギーが出てくると、身体症状が出てきます。非常に疲れます。この時期にしっかり手当てする必要があります。身体管理をするということは、精神的に非常にエネルギーを与えることだと思っています。生まれて初めて病院に入った患者さんは慣れないことばかりで緊張の連続です。次に何が起こるかわからない。身体を丁寧に診ることによって、少しは普通の生活の安心感を与えたい。親子でも、「お母さん、下痢をしてね」と子どもが言った時に、「薬のんどき」と言うか、「どれどれ」とおなかをさわって、顔色を見てくれるのとでは親子関係はずいぶん違うでしょう。精神科の医師や看護師は特殊な能力をもっていなくていい。きちんと身体を診て、きちんと挨拶して普通に患者さんを扱う。そのほうが関係はいいです。患者さん一人一人に挨拶するということは、相手を人間として認めているということです。入院の時はできるだけ自分で外来から病棟へ連れて行き、師長さんに「今度、入院を決められました~~さんです。よろしくお願いします。」と伝えます。最初が大事だし、そういう小さいことの積み重ねが大事なのです。家庭でも大事件が毎日あるわけじゃなくて小さいことの積み重ねです。「おはようございます」からはじめる。挨拶を返さない患者さんもちゃんとわかっています。ただ返すエネルギーがないだけです。患者さんのことを難しく考えすぎないほうがいい。
回復期は疲れる
発病でたまった疲れはどこへ行くのか。なぜ患者さんはあんな疲れやすいのでしょうか。患者さんが働いているのをみると、リズムに欠けています。ちょっと働いて、ちょっと息抜き、また働くというリズムがなくて、一様にずっと働く、あるいはドーと働いてパッと休む。でも休んでいる間も緊張は続いている。そんな感じ。で1週間ぐらいで「もたない」と言ってくる。
郵便局や銀行で働いている人たちを待合でずっと見ていると、うまくフッと力を抜いたり、軽く気分転換しています。例えば手洗いに立つついでに仲間と話をしたり。そういう風に気を抜いている。基本的に人間は力を入れたり抜いたりすることで「もっている」のだと思います。このように小さな休憩をはさむとか、ものごとを行う段取りや優先順位を工夫するだけでガラッと様相が変わるでしょう。これはリハビリの重要なポイントです。抽象的に言うだけではだめです。具体的にそのつど、根気よくアドバイスする必要があるでしょう。
患者さんは「忘れること」ができない
何年も経過している患者さんでも、急性期はせいぜい2~3ヶ月と意外と短いものです。その一方で患者さんは急性期のことを非常によく覚えています。どういう体験をしたか、医療者が何をどのような調子で言ったか、ちょうど柔らかい粘土に押し付けた模様のようにそのまま記憶しています。ふつうは過去の思い出というものは自分に都合がいいように変わっています。嫌な思い出が薄れていくことで人はどうにか生きていけるのかもしれません。都合よく話が変わっていくのは一種の健康さです。その人が幸福かどうかに関わらず思い出は「楽しいこと6、中立なこと3、嫌なこと1」だそうですが、患者さんにはどうも当てはまらない。「生まれてからいい思い出が一つもない」と言う方がけっこういる。実際そうかもしれませんけど、「都合いい思い出が残る」ということが起こらないのかもしれません。というのはそういう方でも回復してこられると、例えば「一人で菜の花畑を歩いていた。空が晴れていて、鳥の声が気持ちよかった」というような、ちょっと寂しいけどすっきり澄んだ思い出が出てきますから。
嫌なものは一度で懲りる
食べ物の本を読んでいたらこんな話がありました。自分の好みの味、好きな食べ物というのは徐々にできていくのだそうです。何度か食べていってだんだん「いいな」と思う。最初に飛びついて「おいしい!」と思ったものはだんだん飽きてくることがけっこうあるわけで。好きなものは徐々に形成されてくる。
ところが嫌いなものは一度に形成されてしまう。例えばたまねぎを食べて一度で「これはかなわん」となる。このような非対称性は、実は体験一般にいえるのではないでしょうか。一度でたまらんと思うのは、たぶんそうである必要があるのでしょう。例えば地震というものは何度も経験してだんだん怖くなるものではない、一度で忘れられない記憶を残す。おそらく精神のバランスが崩れるという体験にも同じ力があると思います。
この「好きになるときと嫌いになるときの違い」は大切だと思います。常にあてはまるわけではないでしょうけど、一目ぼれよりも、だんだん好きになって「振り返れば君がいた」というほうが安全で長続きする確率は高いでしょうね。急に好きになるとイヤになるのも突然イヤになることが多いらしくて。
疲れている患者さんに何を言うか
さて急性期が終わったあとの1週間くらい、ほんとうに治ったような気がする。元気になって表情もキラキラする時期がある。「もう明日からでも働ける」と言います。しかしそれで出勤させると1週間ももたない。また疲労がどっとでてきて回復にまた時間がかかる。
その後、消耗の時期が来ます。この時期は筋肉そのものが1つ1つの微粒子まで疲れているような疲れではないでしょうか。それで何をしても疲れる。やがて疲れが減ってくると、日々の行動やストレスの度合いで疲れる程度が変わってくる時期がおとずれます。
水深が深いときは底に何があってもあまり変わりません。水が覆っていますからね。「とにかく疲れている時期」はこういう状態です。やがて水深が浅くなってくると、底の状態によって変化が出てくるわけです。日によって疲れに違いが出てくる。これは回復のしるしです。
患者さんは自分の状態をどのように捉えているのでしょうか。聞いてみると、「自分はあせりのかたまりになっている」と言う。ただ何にあせっているのかははっきりしない。「ゆとりがない」という表現は、単純ですけど割と通じます。この「焦り」の中にも筋肉感覚が混ざっているのかもしれません。
次に患者さんのしんどさを二つに分けます。「しんどい」というかたはけっこういますね。そう言われたら「そのしんどさは硬い? それとも軟らかい感じ?」と聞く。この二つはまったく別です。硬いしんどさは『緊張』。軟らかいしんどさは『筋肉はゆるんでいるけどそれを感じない』です。つまりほんとはリラックスした状態なんです。でもアンヘドニア(無感覚)になっており、それを感じない。患者さんが「軟らかいしんどさだ」と答えたら「それはリラックスというものかもしれないよ、だけどあなたは緊張が続きすぎて、しばらくリラックスしなれていないからね。無理ないよね、しばらく待ってごらん」と告げます。また、何かした後に、疲れは翌々日に出ることが多いです。体がほぐれ、リラックスするのにそれだけ時間がかかるのでしょう。
周囲の人はチクチク刺激しない、独りの空間も必要
これは周囲の人たちの問題です。患者さんがしんどいと感じて焦ってしまう理由の一つに家族からのプレッシャーがあります。「早くあなたに働いてもらわないとね」「これからのことをどう考えているの」などという慢性刺激を家族が与えてしまう。これは硬い緊張を持続させることになります。
では、生涯ブラブラしていてもいいのかということですが、「その時期が来たらおのずとわかる」「今は見えないものが見えてくる」という意味のことを告げます。だいたいにおいて統合失調症の患者さんは『先案じ型』で将来ばかり案じています。うつ病の人は「あのときああすればよかった」という『後悔型』ですが、統合失調症では先へ先へと考えが行ってしまう。先案じ型であることは患者さんも自覚しています。「どんどん考えが先に行ってしまう」と言います。病気のはじまりの時もあらゆる可能性を考えて思考がどんどん枝分かれしていき、とうとう自分でコントロールできないくらいになってしまいます。つまり統合が失調するわけです。そういうときは平凡ですが「あまり先に考えても、そのとおりになるとは限らんものなあ」「最悪のことがいちばん実現するとはいえんものなあ」とポツンとつぶやく。ちょっと含みを持たせ、視野を広げる、軟らかくすることが大事です。
家族のかたに特に強調すべきことは、家の中に病人がいたら緊張するのは当たり前だということです。けれど緊張が緊張を生むことがありますので、できたら一日中いっしょにいないことです。それぞれ別室にこもるときがあったほうがいいと思います。
熱病などとは違って、『安心して一人でこもれる場所』は本人にも家族にも絶対必要。退院が近づいた患者さんに「安心して治れますか」と聞くと言葉を濁す方が少なくない。統合失調症は「アンテナの病い」とも言えます。まったくの雑音まで気にしてしまったり、何気ないしぐさを重大視することがあります。ですから批評、批判のたぐいは控えましょう。批評され続けて心に批評ダコができている人も少なくありません。
趣味のある人は見込みがある
例えばアルコール依存症で、見込みのある人は「好み」がある人です。好みの銘柄がある、ひいきの野球チームがある。とにかくそういうもの。趣味がある人。逆にアルコールならなんでもいい人、お酒を味わうのではなく、とにかくよっぱらってすべてを忘れたい人は、残念ですがよほど何かが変わらないとダメですね。「うまく酒に見放される」といったことが大事です。幻聴や妄想の内容についてあまり触れるべきではないのは、そんなものに凝っていたら抜けられなくなるからです。幻覚だって一種の依存状態といえますから。お酒や賭け事なども、自分がしたくてしているうちはまだいいのであって、「しているのかさせられているのかわからなくなる」と危ないですね。
幻聴に耐える力
「物事を被害的に捉えるか」の研究で、統合失調症群と一般群であまり変わらなかったそうです。どちらもけっこう他人のせい、社会のせいと考える。考え方自体はそんなに違わない。違うのは「その重みに耐えられるのか、耐えられないのか」でしょう。幻聴が聴こえていても気にしない人もいれば、わずかな幻聴でダメになってしまう人もいる。幻聴への対処法として、外に出してしゃべってしまう方法もあれば、内に溶かし込んで受け入れてしまう方法もあります。リラックスするようになると弱まりますね。自分だけが特別な人間でないと考えると、緊張が解けるのか、不思議に静まる場合があります。逆によくなることに、現実に戻ることに耐えられない方もいます。急に治るかたは物凄く危ない。自殺はたいていよくなって主治医のもとを離れた後です。
ある患者さんは5歳くらいの頃に父親が政治に憤慨して割腹自殺をなさった。彼はそのことを背負って生きてきました。「よくなったから故郷の病院で薬をもらう」と主治医から離れた。それからしばらくして再び主治医に会いに来て「やっと父が死んだ年齢を超えました。非常に楽になりました」と言われた。一月くらいたって母親から分厚い手紙が届いた。彼は自殺していました。急激な変化は出来るだけ避けてゆっくりさせる。むしろ「そんな急によくならないように」というと妙ですが、加速度がつかないようにすることが重要です。
慢性患者さんで「治らないだろう」と思われていた方が意外に年月を経てよくなっていくことがあります。前の主治医の努力かもしれないし、今の主治医のおかげかもしれない、年月がたってやっと患者さんの環境が整理されて治れるようになってきたのかもしれません。逆に、一見いいと思ったら実はそうではなかったという場合もあります。急によくなるようにみえるときは危ないです。変化するというのは自動車がカーブを曲がるようなものです。スピードを落とさなければ曲がれない。よくなりかけたときは煽るのではなく、むしろブレーキ。治療とは山に登ることではなく、加速度がつかないようにしながら山からおりることなのです。そして戻るところは平凡な里です。山頂ではありません。回復とは平凡な里に向かって、足を一歩一歩踏みしめながら滑らないように降りていくことなのでしょう。